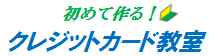(PR)
ポイントを使って取得した資産や支払った費用の会計処理
近年、多くの小売店やネットショップでポイントサービスが導入されています。ポイントの使い道は様々ありますが、多くのお店で買い物代金の支払いに使えます。
法人や個人事業主も、スーパーなどの小売店やネットショップで事業用資産を取得したり、消耗品費などの経費の支払いをし、ポイントを獲得することがあります。このようなポイントは、法人でも個人事業主でも一種の資産となるので、どのように会計処理すべきかが問題になります。
ポイントの性質
小売店やネットショップが発行するポイントは、将来の買い物代金を減額する性質を持っていることから、ポイントをもらった側にとっては将来の買い物時に値引きを受ける権利を取得したのと同じです。
したがって、買い物をした時にもらったポイントは、その段階では買い物代の値引きを受けられません。あくまでポイントは、将来に値引きをしてもらえる権利を有しているだけです。
ポイント獲得時の会計処理
法人や個人事業主が、収益を認識するタイミングは、基本的に商品や製品を販売した時です。したがって、商品を仕入れた段階や製品の製造段階では収益は認識されません。
商品を仕入れても販売しなければ収益が計上されない以上、ポイントをもらった段階では収益は計上されません。そのポイントを使って商品を仕入れ販売した段階で、ポイントを使った値引き額分だけ利益が多く計上されます。
なので、ポイントを獲得した時点では会計処理をする必要はありません。ただし、会計処理はしなくとも、ポイントは法人や個人事業主にとっては財産的価値があるので、未使用のポイントがどれだけあるのか、ポイント有効期限がいつまでなのかは、しっかりと把握しておく必要があります。
ポイントを使って資産を取得した時の会計処理
商品を仕入れるたびに仕入先から将来の仕入時に代金支払いに充当できるポイントが還元されるとしましょう。
この場合、ポイント獲得時の会計処理は不要ですが、ポイントを使って商品を仕入れた場合には、ポイント分だけ値引きがあったものとして会計処理しなければなりません。
例えば、4月10日にクレジットカードを使って商品を仕入れたとします。仕入代金は1,000円ですが、そのうち100円分を貯まっていたポイントで支払いました。この場合の会計処理は以下のようになります。
4月10日の会計処理
- (借方)
仕入 900円 -
(貸方)
買掛金 900円
「仕入値引」勘定を使っている場合の会計処理は以下の通りです。
仕入値引を使う場合の4月10日の会計処理
- (借方)
仕入 1,000円 - (貸方)
買掛金 1,000円
- (借方)
買掛金 100円 - (貸方)
仕入値引 100円
また、課税事業者が「仕入値引」勘定を使っている場合の会計処理は以下のようになります。なお税率は10%で計算しています。
課税事業者が仕入値引を使う場合の4月10日の会計処理
- (借方)
仕入 910円
仮払消費税 90円 - (貸方)
買掛金 1,000円
- (借方)
買掛金 100円 - (貸方)
仕入値引 91円
仮払消費税 9円
ポイントで経費の支払いをした場合の会計処理
ボールペンやコピー用紙などの文房具を購入した時には、消耗品費として会計処理します。出張時のホテル代を支払った時には、旅費交通費として会計処理します。これら費用(経費)の支払い時にポイントを使った場合も、基本的に資産の取得と同じように会計処理します。
例えば、6月1日にネット通販で事業に必要な筆記具とノートを購入したとします。代金は2,000円ですが、そのうち200円分はポイントを使い、残額1,800円をクレジットカードで支払いました。この場合の会計処理は以下の通りです。
6月1日の会計処理
- (借方)
消耗品費 1,800円 -
(貸方)
未払金 1,800円
200円分のポイントを使っているので、2,000円から200円を差し引いた1,800円が消耗品費として計上されます。なお、課税事業者の会計処理は以下の通りです。
課税事業者の6月1日の会計処理
- (借方)
消耗品費 1,637円
仮払消費税 163円 -
(貸方)
未払金 1,800円
複数の経費をポイントで支払った場合の会計処理
ポイントを商品の仕入にだけ、あるいは消耗品費の支払いだけにしか使わないと決めておけば、会計処理は上記のようにすれば問題ありません。しかし、1回の取引で仕入や消耗品費の支払いが発生する場合、ポイントは仕入から減額すべきか消耗品費から減額すべきかが問題になります。
複数の勘定科目にポイントの支払が影響を与える場合は、ポイント使用前の代価を基準にポイントの値引額を案分すれば良いでしょう。
例えば、7月15日にネット通販で、コピー用紙500円と書籍1,000円を購入し、150円分はポイントで支払い、残り1,350円はクレジットカード払いにしたとします。なお、コピー用紙も書籍も事業に必要なものとします。この場合は、ポイント使用前の金額を基準にそれぞれの値引額を計算します。
- コピー用紙の値引額
500円×150円/(500円+1,000円)=50円 - 書籍の値引額
1,000円×150円/(500円+1,000円)=100円
上記の計算結果をもとに会計処理すると以下のようになります。
7月15日の会計処理
- (借方)
消耗品費 450円
新聞図書費 900円 -
(貸方)
未払金 1,350円
また、課税事業者の場合は以下の通りです。
課税事業者の7月15日の会計処理
- (借方)
消耗品費 409円
新聞図書費 818円
仮払消費税 123円 -
(貸方)
未払金 1,350円
上記のようにポイントの使用が複数の勘定科目に影響を与えると案分計算に手間がかかります。少しでも記帳の手間を省くためには、ポイントの使用は特定品目の取得に限る社内規定を作成しておくのがおすすめです。